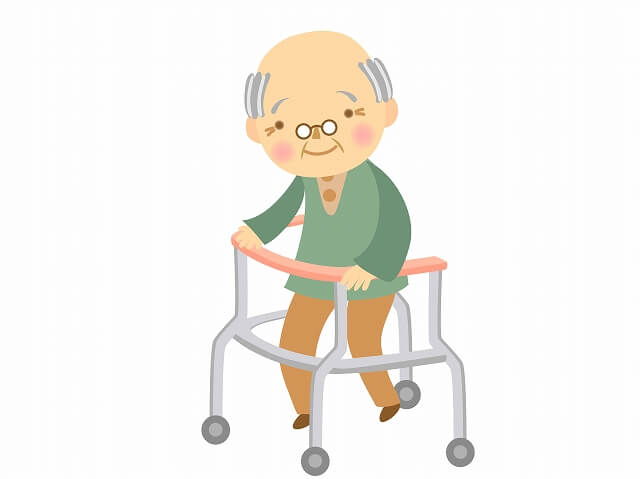歩行器を見かけることが最も多いのは病院においてではないでしょうか。体の周囲をコの字型に守るようなフレームに4本の脚部がついているというのが、歩行器の基本形です。
歩行器 にはどんな 種類 があるのでしょうか。その特色と共にみてみました。
身体機能に合わせて選ぶのがポイント歩行器の種類
持ち上げ型歩行器
持ち上げ型歩行器は固定型歩行器とも呼ばれていますが、その名の通り、使用する際に両手で歩行器を持ち上げて前に進めます。
歩行器を持ち上げて前に着地させる際に体を歩行器に預け、グリップに体重を移動させます。次いで患側の足、健側の足の順番で足を運びます。体を歩行器に預けることによって、患側の足にかかる体重の負荷がおおよそ半分になるとされています。
上腕の筋力はあるものの、杖歩行はできない場合に有効な歩行器です。高齢者によくみられる疾患としては、大腿骨骨折・リウマチ・膝関節症などが考えられます。高齢者に限りませんが、下肢をギブスで固定された場合など、体を曲げたり、ねじったりできない場合にも有用でしょう。
まず、持ち上げることが必須になってきますので、高齢者が使用する場合には、上腕にそれに耐えうる筋力があるか、バランスがとれるかということがチェックポイントとなってきます。
持ち上げ型歩行器には折り畳みのできるものとできないものがあります。折り畳みができるものの方が若干重くなってしまいます。
昨今では、従来のアルミ製のものばかりではなく、マグネシュウム合金やカーボンファイバーをフレームに利用することによって本体の軽量化と安定化の両立を図る工夫がこらされています。
高さと幅の調節の効くタイプやグリップ部分が2段階の高さになっていて立ち上がりにも便利なものもあります。小柄な方や家庭内での使用を考慮して軽量でコンパクトなミニタイプもあります。
フレームの内側に椅子を付けて疲れた時に休息したり、浴室での着替えに利用したりと生活のさまざまな場面に便利に使えるようになってきています。
交互型歩行器
交互型歩行器は基本的な構造は持ち上げ型のものと同じです。相違点は体の周囲のフレームを左右別々に動かすことができることです。
右側の歩行器のフレームを前に出し左足を前に、次いで、左側の歩行器のフレームを前に出し右足を前に出すという動作を繰り返して前進します。
この動作は人の歩行運動に近いものがありますが、持ち上げ型歩行器では3動作であったものが、4動作になるため、身に着けるのにやや困難さを伴うことがあるかもしれません。
四肢の筋力低下がみられる場合に有効な歩行器です。高齢者によくみられる脳神経系疾患のために姿勢のバランスがとれない場合や変形性脊椎症や変形性膝関節症などの骨関節疾患の場合に有用でしょう。
歩行運動に近い運動を要求されるだけに、全身のバランスをとる必要がありますので、体があまりにもスムーズに動かせない・バランスが極端に悪いといった場合には使用に適さないこともあります。
前輪歩行器
前輪歩行器は持ち上げ型歩行器の前脚にキャスターがついたものです。
後脚を少し上げて、前輪を使って前方に進め、その際、グリップに体重をかけることでストッパーをかけて歩行器を固定します。
次いで患側の足、健側の足の順に足を運びます。持ち上げ型歩行器の安定感という利点にキャスターをつけることで上半身の筋力が弱くても使用できるという利点を加えたものといえます。
歩行器を前に出す際に、腕や体幹の筋力があまりに弱い場合には使用に適さないこともあります。
四輪歩行器
四輪歩行器は持ち上げ型歩行器の4脚にキャスターがついたものです。中には、前輪はキャスター、後輪は固定輪をつけているものもあります。移動という観点では楽に長い距離を歩くことが可能になります。
グリップを少し持ち上げて前方に進め、グリップに体重をかけてストッパーを効かせて固定します。次いで、患側の足、健側の足の順に足を運びます。
四輪歩行器の中にはブレーキのついていないものもあります。ストッパーが効かないので歩行器が思いがけず先に進んでしまい、体が取り残されるということが起こる可能性があります。
上肢の筋力低下がみられる場合にも使用することができ、病院やリハビリ施設で最も目にする機会が多いのはこの四輪歩行器でしょう。体の周囲のフレームの形からU字型歩行器と呼ばれることもあります。
歩行器を選ぶには
高齢者にとって、移動の自由は大変重要な問題です。歩行器に体を預けることで体重が分散し、痛みや筋力低下があってもその負担を減らすことができます。
また、運動機能や神経の反応速度が低下していて、ふらつきがみられるような場合にも体重を支える面積が広い歩行器を使用することによって姿勢が安定します。
体の状態と症状によって最もよい歩行器を選び、サイズや高さも調節することが、思わぬ事故を防ぐために必要になってきます。
歩行器を選ぶ際には、医師・理学療法士・福祉用具相談専門員などの専門家の意見を求めるのがよいでしょう。
まとめ
身体機能に合わせて選ぶのがポイント歩行器の種類
持ち上げ型歩行器
交互型歩行器
前輪歩行器
四輪歩行器
歩行器を選ぶには